Date : 2025年3月8日
GO▶︎ganic PEOPLES! #07
SUMMER SCHOOL とうもろこし 代表 馬場 美帆さん
写真・文 / 戸田 コウイチロウ(GO GOTSU.JP編集部)

「子供たちの未来のために、豊かな自然環境と安全安心な食の確保を。」をスローガンに掲げ、有機農業を実践する生産者とオーガニックな食や暮らしのあり方を提唱する民間の有志メンバー、それらをとりまとめる江津市農林水産課。仲間づくりや有機農業を目指す人材の発掘、オーガニックに対する意識醸成といった啓発活動を三者で手を取り合って進めていく有機農業推進プロジェクト、それが『GO-ganic』(ゴーガニック)だ。
GOGOTSU.JP編集部ではこのプロジェクトの中心的な役割を担い、啓発活動を続ける方々のお話をお聞きし、連載としてお届けします。題して『GO▶︎ganic PEOPLES!』。
第7弾は2021年にフリースクール「SUMMER SCHOOL とうもろこし」(以下、とうもろこし)を立ち上げた代表の馬場美帆さん。元小学校教諭だった馬場さんは石見で生まれ育ち、過疎化していく地域を「自分ごと」として危機感を持ち、子どもたちと触れ合うことでなにか解決策を持ちたいという一心で教師の道を志す。地域が好きで、特にふるさと教育に強い関心があったからだ。
数年間の教師生活の紆余曲折を経て、自らの理念を掲げるフルースクールを立ち上げた真意とは一体なんだろう。GO-ganicでの馬場さんの役割、近い価値観を持つもの同士が集い形成されていくコミュニティ、教師経験があったからこそ見えて感じる地域と学校、大人と子どもの関係性。自らの身体に起きた変化。ときには「とうもろこしの教室」にもなるご自宅まで話を聞きに伺った。
『学級崩壊も経験しましたし、振り返ると無理をしてやっていたなと思うこともあります。それでも今、思い出すのは学級崩壊していた最中にひとつだけうまくいったなという授業があったことですね。』(馬場さん)

「私は元小学校教諭です。教諭という仕事になったのは石見に(Uターンして)帰ってくる子どもたちを増やしたい、過疎化をできるだけ防いでいきたいという気持ちがあったからなんです。私が中学生の頃、通っていた中学校がなくなるとその当時言われていました。中学校がなくなるということは村がひとつなくなる、ということは浜田もなくなるのかなという危機感をおぼえました。
自分が教諭になって、子どもたちに情操教育をしていくことが自分のやりたいことなんだと考えるようになりました。教師になること=目的のための手段のような感覚に近かったのかなと思いますが、それぐらい私は石見という地域が好きなんです。」
(馬場さん)
大学卒業後、希望通り学校教師という仕事に就いた。勤務先は江津の小学校だ。しかし、時間が経過するにしたがって教科書に載っていることをただただ教えて教壇に立ち続けることに疑問を持つようになった。私は本当にこれがやりたいことなのか。
「学級崩壊も経験しましたし、振り返ると無理をしてやっていたなと思うこともあります。それでも今、思い出すのは学級崩壊していた最中にひとつだけうまくいったなという授業があったんです。江津の様々な分野のまちづくり支援を行っているNPO法人てごねっと石見さんと一緒に作った授業で『江津の未来』をテーマにしたものがありました。『どうやったら江津に人が増えるだろう?』ということを考える授業です。ここでは子どもたちは自分の想いをみんなに聞いてもらえるし、面白いことをやっている大人たちと話もできる。主体的になって自分たちで調べたり、書いたり、話し合ったり、みんながとても授業に集中していたんです。」
(馬場さん)
教師として教壇に立つことをしたかったというよりは、面白いことをやっている大人、なにか気づきを残してくれるような人たちと石見の子どもたちを繋いでいくこと。これが自分がしたいことだ、自分が得意なことなんだと感じた。そのイメージをもって授業を行うようになっていくとこれまでとは違う授業のあり方が見えてきた。子どものやる気や目の輝きがいい風に変わり、江津が好きという子どもたちも増えた。

「それと同時に『生きる力』をもう少しつけさせてあげたいと思う子どももいました。例えば給食を残す子どもがいますよね。残すのことの良し悪しのことよりも『誰が作ってくれたんだろう』とか『どういう想いがあるんだろう』ということを知らない、教えてあげられていないことが問題なのかもと思ったんです。
また、生きるということを考えたときに仕事をしてお金を稼ぐということをどこかで学ぶ必要があります。それがわからないからし、知ったり考えたりする機会が少ないし、まわりにそういうことを気に掛ける大人もいないから公務員や銀行員といった目の前に見えるものでしか判断しなくなってしまう。それだけだと江津や石見に失礼ですけどワクワクする未来は描けないですよね。それじゃあ県外に出て行ってしまうよねと。
学校の中では教えていないことを指導していきたいと思うようになっていきました。それで教諭という仕事を終えた後、『SUMMER SCHOOL とうもろこし』(以下、とうもろこし)というフリースクールを始めたんです。」
(馬場さん)
「今の子どもたちって自分がやりたいことを言えなくなっている状況があるんです。それは本人の問題でもありますけど、まわりの大人たちも『子どもはなにが好きなんだろう』『今どんなことに興味があるんだろう』ということに気づいて知ってもらいたいなと思います。」(馬場さん)
2021年の夏に始まったとうもろこし。「こんなことをやりたい」と周囲に話し始めていった。知人・友人に「広報」していくうちにたくさんの協力者が現れ始めるようになる。これはきっと馬場さんの人徳や人柄だろう。誰かのなにかを応援する江津という町の雰囲気もあるのかもしれない。なにより元教諭(教育者)というキャリアと信頼性がある。フリースクール開業への道はゆるやかに開けていった。
「すぐに資金を用意することはできなかったのですが、本当に色々な方々が協力してくださったんです。(私との)信頼関係があるからね、と言ってくださる方がたくさんいました。それはとても嬉しいことでした。」と数年前のことを振り返る。
主な対象は市内市外の小学生たちだ。学校が夏休みになるととうもろこしの出番となる。お盆期間と週末を除くほとんど毎日、自主学習やワークショップ、海遊びや散策などの「クラス」が用意され、学ぶ、食べる、作る、知る、遊ぶなどの要素をふんだんに取り入れたとうもろこしという自由な学校。子どもたちは夏休みという日常から解放され、いつもとはちょっと違う異年齢の友達同士で過ごす夏に興奮する。

毎日のお弁当は保護者の負担が増えるからということに配慮し、自分たちでおにぎりを握ったり、江津工業高校の学生たちと「流し素麺機」を一緒に作って素麺をみんな食べる日もある。そのおにぎりのお米は誰がどんな方法で作っているのかをきちんと伝え、春には田植えも経験させ、秋には収穫も体験させる。知り合いはもちろん、他薦もあわせて講師として協力してくれる地域の大人たちに声をかけ、授業を企画し、共同で「クラス」をつくるのだ。子どもたちは毎朝江津市内の様々な場所に集合し、夕方まで時間を過ごす。
夏休み期間中、我が子をどう過ごせておこうかと悩む保護者は多い。特に夏季プールがなかったり、近所に子どもが少ない地域の子どもは遊ぶ環境も制限されるし、学童も夏休みだけ行くということも難しい現状がある。とうもろこしのような「居場所」は願ったり叶ったりではないだろうか。
「私がこうやってたくさんの協力者に支えられたことは江津のとてもいいところですよね。今度は子どもたちがあれしたい、これしたいと思った時に実現させてあげられる大人をたくさんつくりたいということを考えました。
というのも、今の子どもたちって自分がやりたいことを言えなくなっている状況があるんです。それは本人の問題でもありますけど、まわりの大人たちも『子どもはなにが好きなんだろう』『今どんなことに興味があるんだろう』ということに気づいて知ってもらいたいなと思います。だから大人と一緒に体験することを『繋ぐ』ということを大事にしています。
次に子どもたちが自分の言葉で『やってみたい』を口に出せるようにしていき、伸び伸びできる環境や場をつくってあげる。自分のことは自分で考えられる、自分で行動できる力をつけさせてあげる。その結果として家庭の負担を減らしていくということにも貢献したいと思っています。『生きる力』を作ってあげることですよね。」
(馬場さん)
このイメージでとうもろこしを運営しているのは企業理念のようなものだ。判断力を養うことや知識をつけること、きちんと意思を持って選択できることといった「体の土台づくり」。そして慌ただしい学校生活を送る中でこういう場所に来てたまにはぼーっとしたり、新しい体験をしたり、いつもの学校とはちょっと違う気持ちになったりすることで得られる「体のゆとりづくり」が大事にしていることだという。

午前中は活動の時間、お昼以降は遊びの時間とメリハリをつけている。なんでもいいよいいよとする仲良し集団ではなく、厳しくいうときは理由もあわせてしっかりいう。筆者も何度も現場に行ったことがあるが、馬場ちゃんのことが好きという子どもは多い。それはきちんと目を向けてコミュニケーションし、向き合っているからだろう。子どもは大人の言動を大人が思っている以上によく見ているものだ。
2024年時点で事業は4年目となり、宣伝活動をすることはなく、口コミだけの評判と集客で始めた頃よりも3倍4倍ほどの人数の子どもが集まるようになった。食事や健康、からだのことを学べるクラスも続けている結果、食事に気を使うようになって自分で料理を始めた子どももいる。
保護者からは「土日が楽になりました。」と言われるようになった。子どもたちからはやりたいことが口々に出るようになってきた。また、とうもろこしが始まった時期にいた子どもは今や中学生。来年度江津工業高校に入りたいと受験を決めた子もいるそうだ。「お泊りやったり、みんなでフェリーに乗って隠岐に行ったり、たしかに大変にもなってきたんですけど、それでも子どもたちからやりたいことがたくさん出てきたり、新しい体験ができるようになってきたし、やっぱり嬉しいですね。(笑)」と充実し、手応えを感じていることがその表情から十分伝わってくる。今いる子どもたちが大人になったときにどんな風に成長しているのか、馬場さんは今から待ち侘びている。
話を少し前に戻そう。教諭だった20代中盤までの馬場さんと現在。とうもろこしの活動をする前はどんな生活習慣の意識があったのか、気になったのでお聞きしてみたい。
「自分の変化のきっかけですか。それはもう、反田さんとの出会いが一番大きかったです。教員2年目の頃だったので20代前半、2014年頃ですね。食生活でいえば、一般的でしたけど、私の祖母が無農薬で農業をやっていたこともあって、食への意識は別に全くないというわけではありませんでしたし、興味はありました。小学3年のクラスで農業について授業をしていたときに『生徒たちを畑に連れて行こう、誰か面白い方いないかな』と思って生産者さんを探していたんです。
給食に使っている食材や野菜についても調べました。無農薬のものは使われていないことも知って衝撃を受けたりもして。そんなときに反田さんに行き着いたんです。野菜やお米の話、栽培の話をしてくださって。とにかく面白かったんです。教科書に載っている農業のことしか私は知らなかったわけですが、それしか知らなかったらダメになるなと思ったんです。(笑)そこから自然栽培にとても興味を持つようになりました。」
(馬場さん)
『私のお腹の中にいた赤ちゃんが病気になったんですけど、その子が病気になっていく様子が自然栽培の腐敗実験の様子ととても似ていたことに気づいたんです。(馬場さん)
自然栽培に腐敗実験については青森のりんご農家である木村秋則さんの話が有名だ。詳しくは触れないが、自然栽培と野菜と一般栽培の野菜を一定期間そのまま放置すると自然栽培で育てた野菜は腐らないが、一般栽培の野菜は腐ってしまったという実験だ。一般栽培は化学的なきつい刺激臭がするそうで、これは農薬などの化学物質だとする見解がある。こういったことについても反田さんは実証済みで説得力もあった。
「私のお腹の中にいた赤ちゃんが病気になったんですけど、その子が病気になっていく様子が自然栽培の腐敗実験の様子ととても似ていたことに気づいたんです。もしかして自分が食べてきたものによって子宮の中がまるで土の中と同じ状況になっていたのかな、と感じたんです。食べるものって本当に大事なんだなって。」
(馬場さん)
この体験が自身の転換点となり、食の意識が変わり、勉強するようになった。今となってはそうやって口に入るものが変わると自分の性格も変わっていくことを感じ、お産も、日々の暮らしも心地よく感じるようになっていったという。また誰かと話すときに相手の言っていることも受け入れられるようになったりと自分で驚くほどの変化が訪れる。
「こういう変化が面白くなって、ああ、誰かに話したい!っていう風になりましたね。(笑)」と笑う。人は頭で理解するよりも体感することが一番腑に落ちる。

『私や、私たちの活動を支援してくださる企業へはじめて打ち合わせに伺ったときは緊張して足がカチカチに固まりました。』(馬場さん)
とうもろこしを運営し、教育や子育て、食や環境、地域のことなどが身近になるにつれて同じ価値観をもって共有し合える同世代のコミュニティが自然と出来ていった。そこで生まれたのが『コドモミライごうつ(当時の名称は「コドモミライいわみ」)』だ。一体どんな団体でどんな活動をしているのだろう。
「活動のきっかけは、とうもろこしのお昼ご飯のことでした。(都野津にある自然食品店)希樹の寺井憲子さんに相談したときに『江津の子どもたちの食のことを考えたり、作ってあげるような活動をしていきたい』という話を憲子さんがしてくれたんです。なにか一緒に活動しようという流れになりました。
他に賛同してくれる人いるかなとなったときに嘉久志町の「HAIR&BODY 心 くくる」の石田智子さんや「もぐもぐキッチン」の山内香織さん、「量り売りSalema」の今﨑希さんも一緒に活動するようになっていきました。そうやって繋がりができていくうちに平下智隆さん(株式会社三維の代表取締役)や平下洋子さん(同社・代表取締役会長)と出会うきっかけが出来ました。はじめて打ち合わせさせていただいて会社に伺ったときは緊張して足がカチカチに固まりました。(笑)
とうもろこしの活動に寄付をしてくださったり、コドモミライごうつのことや描いていることにも共感してくださいましたし、『女性が活躍できることはこの地域のためにもとても良いこと』とおっしゃってくださました。」
(馬場さん)

のちに株式会社三維からサポート受け、映画会やマルシェなどのイベントを開催するに至ったことはこれまで本サイトの特集記事でお伝えしたとおりだ。そうやってできていったコドモミライごうつは市を跨いで「コドモミライはまだ」にも繋がっていった。
オーガニック給食への導入・転換を目的として市内の学校給食をリサーチをしたり、給食センターへ足を運んだり、教育委員会を訪ねては子どもたちの食について意見交換などをするうちに社会が少しづつでも変わらないと自分たちの活動で何かを変えていくことが難しいことを感じる。
目に見える活動として「地域食堂」というイベントをスタートさせた。地域食堂は、地域の食材を使って地域の人たちの手作りによる、誰でも食べに来ることができるポップアップ型の「食堂」だ。ビュッフェで好きなように盛り付けてわいわいとみんなでご飯を食べる。「オーガニックがいいよね」ということだけを話すことが目的ではない。地域のこと、食材や食のこと、なにより子どもたちのことなどをざっくばらんに楽しく話すことができるコミュニケーションの場だ。
「そういう場所で話すとオーガニック給食だけではなく、社会問題や住む町の環境のことなど自分たちの視野も広がっていくんですよね。オーガニック給食の導入から始まった活動が地域食堂や対話することを目的とする『コドモミライ会議』といったものに展開されていきました。これも4年目になったので今みんなで自分たちの活動を振り返りながら整理しています。
オーガニックっていうだけで『値段が高い』とか『意識が高い』とかどうしても『上』に見られることってあると思うんですね。たしかにそういうこともありますけど、きちんと情報が届いていないと私は思っています。どんな風に農作物が作られているのか、生産者の想いもそうですし、有機のものって本当に高いものばかりなの、とかですね。ちょっと食べてみてもらいたいな、ちょっと知識持って欲しいなとかそういうことを含めて情報を届けていきたいなと思っています。」
(馬場さん)
『情操教育とふるさと愛を育む」というテーマについて取り組む。これは自分がやりたかったこと』(馬場さん)

GO-ganicにおいて馬場さんの役割は「情操教育とふるさと愛を育む」というテーマに基づいた活動だ。具体的には保育園に子どもを持つ保護者世代に「どうやったら有機農産物や有機農業に興味を持ってもらえるのか」についてのヒアリングを行っている。生の声を聞きながら自分たちの活動のヒントやGO-ganicの活動へ繋げていくためのアプローチを模索している。
ふるさと教育とは島根県教育委員会が平成17年度(2005年)から県内全ての公立小中学校・全学年・全学級で進めている重点施策で、島根県による公式の定義は以下のとおりだ。
①「ふるさと教育」とは、地域の自然、歴史、文化、伝統行事、産業といった教育資源(「ひと・もの・こと」)を活かし、学校・家庭・地域が一体となって、ふるさとに誇りを持ち心豊かでたくましい子どもを育むことを目的としています。
②自分たちの地域にある課題に正対することで、地域の一員として地域に貢献したり、地域を大切にしたりする心を培っていきます。
※島根県公式サイトより転載
「地域の教育資源(ひと・もの・こと)を活かした教育活動」が要点だ。教諭時代を振り返ると自分はこれこそ自分がやりたいことだったと自覚していたが、学校の中でふるさと教育についてどれほどの教諭が興味関心を持ち、どんな取り組みができるのかということには最後まで疑問が残った。
「なかなか、先生たちもふるさと教育の醸成に時間を割くことができない現状があるのかなと思います。その地域のことを好きでなければふるさと教育と言われてもピンとこない先生もいるでしょうし、結果授業に取り入れてもこなしただけのものなってしまい、子どもたちに響かないものになってしまいますよね。単年度で終わってしまったり。私自身は生まれ育った石見に母校というルーツがあるし、教育事業に関わっている分、もったいないなと感じてしまいます。」
(馬場さん)
『自分の人生を自分で選択しているのに、「やらされている感で動く」というのは時間がもったいない。まず大人たちが楽しむことはすごく大事なことだと思います。(馬場さん)
ふるさと教育始め、例えば有機農業や製品、食の重要性などの啓蒙活動、GO-ganicのプロジェクトを進めるにあたって、有機農業の耕地面積が広がる、有機生産物の出荷額が上がっていくといったことはわかりやすいが、意識醸成についてもう一歩踏み込んで考えてみたい。どういう状態になると人の意識が変わったり、町の雰囲気がGO-ganicによって変わったと感じることができるのだろう。
ただ運営主体メンバーが「有機農業って大切なんです、野菜も美味しいです」と言いたいことだけを言っていても共感を生むことは容易いことではない。元教諭という視点。そこから見る、学校社会や地域社会のこれからについて聞いてみたい。どういう風になっていくと「GO-ganic」が進んでいる、と感じることができるのだろうか。
「今年(2024年)の夏に江津東小学校でPTA有志による夏祭りがありましたよね。『子どものため、ばかり言わないで大人自身も楽しみを見つけ、自分も楽しもう』っていう姿勢のところ。あれはひとつのゴールじゃないかって思います。それと私が問題だなって思うのは多くの場面で『大人がやらされてる感で動いていること』です。
仕事だって自分が選んだはずなのに働かされてるという感覚でやっていたり。使命感がある教師の方も多いですけど、そうではないと方もいます。お互い責任をなすりつけてるなって思う部分も多い。自分の人生を自分で選択してるのに、誰も自分自身の人生の責任を負っていない。 大人がやりたいことをやらないと、子どもたちになにかをさせるっていうことはできません。子どもの責任をとりたくない大人が多くて、学校も地域も責任の押し付け合いのようになっているように見えることもあります。
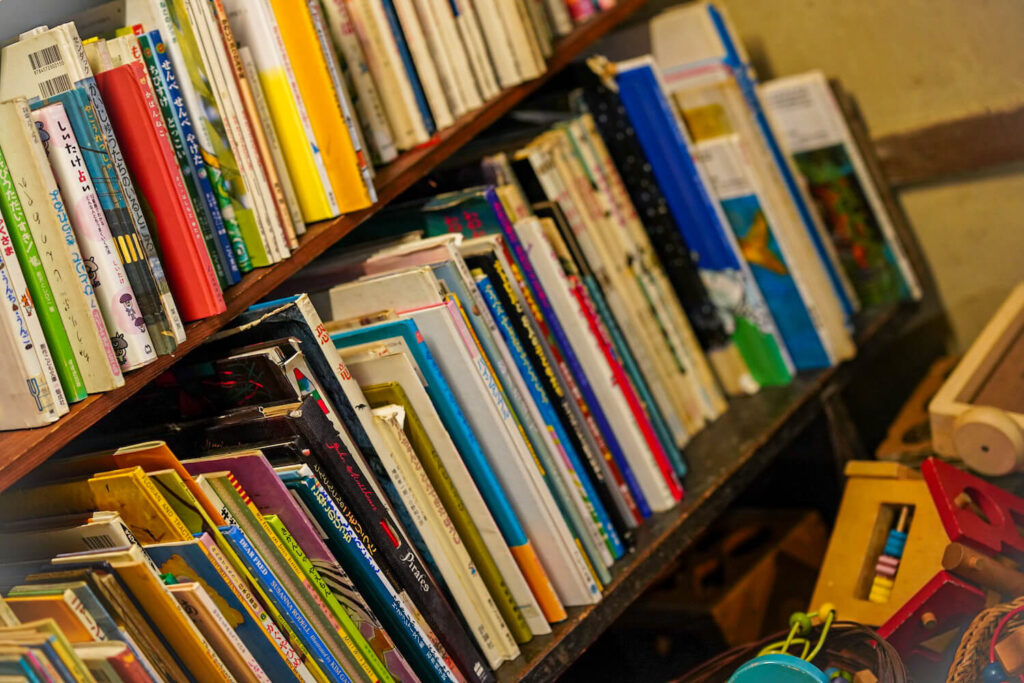
例えば土日に起きた問題があったとして、それを先生に言ったりするんですよ。そんなこと言われても先生たちだってどうにもできないじゃないですか。逆に学校で起きたことを家でどうにかしてくださって言っても『それはそのとき対応しなくてはいけない』ってことにもなる。学校と地域と保護者でどうやって子どもたちを見守っていくかを考えなければいけないのにって思います。
だからとうもろこしをやっていますが、食や心理的なところを通してですけど、お母さんたちの思考を変えていくようなことも意識してやっています。 大切なことはお互い思っていることを受け入れていける相互の関係性です。相手には相手の言い分があるし、お互いに受け止めていくこと。それができていれば問題は起きないんですけど、誰がどんな想いでやっているかわからないからをなんとなくこちらが気にしなければいけない。それが続くとしんどいことにもなります。これしたらこう思われるかもしれないとか。」
(馬場さん)
コドモミライごうつの活動でもオーガニック給食でもふるさと教育でも、なにかを発信したり、新しい取り組みをしたりするときに「なぜやるのか」「どういう想いがあってそうするのか」ということについて相互の理解が届いていないから=コミュケーションができていないから伝わるものも伝わらなかったり、誤解が生じたりするという極めてシンプルな答えだ。
「言ってくれないとわからない」「言ってくれれば理解できたのに」ということで生まれるちょっとした誤解。どんな仕事でも、地域でのコミュケーションでもほんの少し大切に対応したり、丁寧に接することでやりとりが円滑になることはたしかにある。
「学校の中でも効率よいというか上辺だけの会話しかなされていなかったらもったいないですよね。昔はPTAの飲み会とかも多かったって聞きますし。時代が違うのはわかりますが、そういう連携が図れなくなっているんだったらそれはちょっと残念なことですよね。
コミュニティ・スクール(※編集部注:文部科学省による学校運営協議会制度。学校と地域住民等が協力して学校の運営に取り組む制度。学校運営に地域の声を積極的に生かすことができるメリットがあるとされる。)が導入されていくこれからには期待しています。」
(馬場さん)
『偏見かも知れないですけど有機・オーガニックに関わる人たちってあたたかい方が多いって感じるんです。(馬場さん)

江津は他の市町に比べても誰かが新しく始めるなにかを面白がってくれる人が多い、とはよく聞かれることだ。官民一体となって進めるGO-ganicの活動のしやすさはたしかにある。旗振り役を行政自らやっていることも江津らしい。市民が思っていることや考えていることがあったときに耳を傾けてくれるという土壌。これは多くの人が言うように江津という町の特徴であり、無形の財産なのかもしれない。
「GO-ganicの活動もプロジェクトのコミュニティも最高に楽しいですよ。なぜかって私、できないことがめちゃくちゃ多いので、できることだけやってくれたらいいよっていうスタンスがまわりにあるのが嬉しくて。口だけ、アイデアだけ出すタイプで、それに行動が伴うのかっていうとあまり向いてないということを自覚しています。(笑)誰かが準備してくれて私は当日行って役割をこなすみたいな。馬場という人間を受け入れてくれるこの環境ですよね。想いも知ってくれているし、できることできないことも理解してくれてるんですよね。
学校もそんな風にそれぞれができることできないことを受け入れていけたらいいのにと思うんですね。先生も子どもも、そこをみんな無理してがんばってしまう。良くも悪くも真面目なんだと思います。江津は登校拒否児童が結構多いんですけど、そういうことが原因にもなっていると私は感じています。
オーガニックについてはね、ちょっと気になるなとか、一緒に楽しみたいなっていう段階でもいいから『気になるんです』って声をかけてもらえるような存在になれたら嬉しい。意識の高い人たちがやっているなんていう風に思われたくないですし、地域の中で自分の良さとか誰かの良さが掛け合わさって、巡り巡って良い循環が生まれるような、それによって心地よいものができていくようなそんなプロジェクトと地域社会にしていきたいですね。
私の偏見かも知れないですけど有機・オーガニックに関わる人たちってあたたかい方が多いって感じるんです。」
(馬場さん)
(完)





